|
 |
|
|
|
|
|
 |
私の似顔絵
(辛亥新春、昭和58年に
描いてもらいました。) |
|
|
|
でんじろうコラムへようこそ。
唐津の先覚者の一人、辰野金吾の御令息で日本のフランス文学界の先駆者、辰野隆(ゆたか)氏は、明治21年(1988年)「忘れ得ぬ人々」をはじめとした、多くの名随筆を残されている。その中で、郷土唐津のことに触れられていないだろうか・・・とかねてから関心を持っていた。辰野氏については、2012年5月のこのコラム「第107回 東京駅、辰野金吾家の人々」を参照して頂ければ幸いです。 |
|
|
|
|
|
|
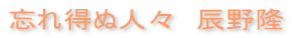 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
講談社学芸文庫「忘れ得ぬ人々」を読んだが見出せぬまま、ひと月ほど前、「唐津探訪」出版に際し、お世話になった佐賀の文化人筒井ガンコ堂さんにお話したら「今僕が読んでいる『忘れ得ぬ人々』に辰野隆氏が帰省した時の文章があるよ」とのこと。早速、その部分をコピーして頂いた。恐らく、文庫本は抜粋版であったのだろう。 |
|
|
その中には、なんと奥村五百子氏と辰野家の交流にも触れられている。 |
|
|
|
|
|
 |
奥村五百子
(明治30年代の写真)
|
|
|
弘化2年(1845)~明治40年(1907)
佐賀県唐津市中町の高徳寺住職・奥村了寛の長女として生まれた。勤王の志士として活動する父の影響をうけ、18歳のころより国事に奔走。明治期に入ると国会活動など様々な活動に尽力し、愛国婦人会を創設した。
また、松浦橋架設、西唐津港開港、唐津鉄道敷設などの公共事業に貢献し、郷土唐津にも多くの功績をしている。
「去華就実と郷土の先覚者たち」奥村五百子(上)・(下)もご覧ください。 |
|
|
|
|
|
|
題して「軍国的回顧 奥村五百子と広瀬中佐」 |
|
|
|
|
|
僕は日清開戦の年(明治27年)に小学校に入学、日露戦争の終わった年(明治38年)に中学を卒業。従って、僕の青少年期は軍国的な思い出が多い。 |
|
|
愛国婦人会創立の奥村五百子刀自と私の両親は、同郷の関係で古くか親交があり、刀自を“お五百さん”と呼んでいたが、僕の耳にはオヨウさんと聞こえていた。僕の兄弟姉妹は刀自を“奥村の小母さん”と呼んでいた。 |
|
|
刀自は年に数回上京する毎に必ず訪れ、泊まっていくこともあった。髪を切り下げにした50恰好の、むしろ小柄な女で、色浅黒く、目は大きく、鼻筋がとおり、若い時には立派な婦人であったろう。 |
|
|
ただ、僕の知った頃の刀自は、挙措も言辞もまるで男、燃え上がる愛国心が、この不惑に達した一女性をますます男性的な活動家たらしめていた。 |
|
|
刀自の談話の中には、常に国家国家という言葉が繰り返され、今日は大隈をやっつけてきたとか、明日は伊藤をうんととっちめてやろうなどと、眉を上げて、父や母に語っていた。僕はそばで刀自の激越な話しぶりを聴きながら、大変な小母さんだなと思った。母はときどき刀自の噂をしては團洲の女形に似ている、あれでお五百さんは舞の名人なのだから、不思議よねと、刀自の帰る後姿を見送りながら、話していたこともあった。 |
|
|
|
|
|
以上は、辰野隆氏が少年時代に接した奥村五百子刀自の印象を語った一説であるが、さすがに名文筆家。五百子の印象を、生き生きと描き、さもありなんと肯かさせる。 |
|
|
因みに、日清戦争から日露戦争までの10数年間は、辰野金吾が工科大学学長、東京帝国大学教授を務めていた期間に相当する。 |
|
|
一方、奥村五百子刀自は、弘化2年(1845年)生まれ。この辰野隆氏の少年時代の刀自の年齢は40~50歳、青春時代、結婚、主婦の時代を経て、唐津に定着し、後世の人々が「五百子の地方的活動時代」あるいは「唐津時代」と称する、唐津に尽くし、いろいろの業績を残している。例えば、満島橋(松浦橋)の建設、舞鶴公園下の海軍の石炭貯炭場の払下げ等々。唐津出身の辰野金吾、天野為之とともに当時の海軍大臣、農商大臣と直接折衝し、成功させている。ちょうど、この頃、年に数回は上京し、辰野家に出入りしたのだろう。 |
|
|
|
|
|
随筆「忘れ得ぬ人々」ではさらに辰野隆氏がはじめて唐津を訪問された様子を伝えている。 |
|
|
|
|
|
日清戦争がめでたく終わって、その翌年の春、僕ら兄弟姉妹は母に従って、郷里なる肥前唐津に帰省した。当時は僕は9歳、母方の祖母が高齢に達し、すでに余命幾何もなさそうとなり、母は父に乞うて久しぶりに故郷の地を踏み、母親を見た。僕らは皆、東京生れで初めての長旅も郷土の風色も悉く珍しかった。帰省中のある日唐津の美しい港を見晴らす「鹽(しお)湯」という旗亭(料亭のこと)で親戚の寄り合いがあった。当時、たまたま奥村刀自も帰省していたので、その会合に加わっていた。宴たけなわにして、誰かが刀自に「お五百さん、久しぶりに、いっちょ踊らんかい」とお国言葉で舞を所望した。すると刀自は言下に「よし舞おう。久しうやらんけん、忘れとるかもしれんぞ」と答えて次の部屋に一旦退いたが、やがて刀自は猖々緋のかいどり(うちかけ)を身に纏い、手に扇をもって再びあらわれると、席に侍していた数名の芸者に向かって「おい芸者衆、いっちょやっとくれんさい」と何か舞の曲を注文した。その舞の名が何であったか少年の僕には判らなかったが、なかなか高級な舞踊であるらしかった。 |
|
|
ただ、日頃、小母さん小母さんと呼んでいながら、むしろ小父さんの感じに近かったこの人にかくまで女らしい優美ジェスト(身ぶり)ができるものかと、子供心にもまったく不思議に思えた。刀自の艶なる風姿には並みいる一同賛辞を惜しまなかった。舞が済んでから、親戚の一老爺が、感に堪えて、「のう、お五百さ、国家のための奔走も立派じゃが、舞は舞でまた、お見事だのう」と激賞した。刀自も一座の喝采が嬉しかったらしく、ひどく満足げに「時々はこういうことん観せとかんと、俺の愛国心も風情が欠くるたい!」と答えて笑った。 |
|
|
|
|
|
当時7歳の少年、辰野隆は、日頃の男まさりの女傑が、あっという間に豹変するのを見て、辰野隆の筆は冴え、奥村五百子の一面を鮮やかに浮き出してくれる。 |
|
|
刀自の生涯は、ほとんど女性としての政治活動が強調されているが、その反面女性としての躾も身に着けられている。 |
|
|
刀自は幼少の頃から音曲を好んで堪能、5、6歳から三味線を習得した。さらに7歳のとき、唐津神社の戸川神官から読書習字を学び、また同じころから三絃舞の稽古に励み、13、14歳頃には唐津においては刀自の舞は町々の評判となっていた。当時は、唐津神社の祭礼に町々から遊芸を奉納する風習があった。刀自はその祭礼に奉納しようと思い立ったが、高徳寺の名のもと、衆人の前で、はしたない町人の様な振舞は許されない、と周囲の反対に、漸く断念したといわれている。 |
|
|
|
|
|
明治27年、辰野一家帰郷の節の寄合で勧められた“塩湯”での余興の踊りは幼年時代に習得した昔とった杵柄だったのだろう。 |
|
|
いずれにしても、奥村五百子の人間像はスケールは大きく、ユニークそして情熱、等々、まことに一女性活動家をこえた何かを感じさせられる。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
参考文献 |
|
|
「忘れ得ぬ人々」 辰野隆 著 弘文堂書房 |
|
|
「辰野金吾の生涯」 富岡行昌 著 郷土先覚者顕彰会 |
|
|
「奥村五百子詳伝」 大久保高明 著 大空社 |
|
|
「奥村五百子の生涯」 富岡行昌 著 郷土先覚者顕彰会 |
|
|
「奥村五百子」 小野賢一郎 著 愛国婦人会 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|


